今回は1983年のフランシス・フォード・コッポラ監督の映画”Rumble Fish“を拝見しました。Matt Dillon主演の青春群像劇ですが、Matt Dillonの心の揺れ動きから、ちょっと距離を置いた突き放したようなコッポラ監督の視線は、暗い、冷徹な、冷静沈着なものだと思います。
1939年のLa Fin Du Jourというジュリアン・デュビビエ監督の作品でも、悲劇的なトリックスターであるミシェル・シモンを、遠くから冷徹に距離を取りながら眺めているデュビビエ監督の冷たい視線が印象に残っていますが、本作”Rumble Fish”を観て、小生は、あの映画を少し思い出しました。
ジュリアン・デュビビエ監督や、コッポラ監督の距離感というものは、人の痛みや苦しみを描きながらも、何処かで共に迷い、共に傷つき、共に倒れてゆくような姿勢は示さない部分があります。
だから、ジュリアン・デュビビエ監督の”La Fin Du Jour”や、本作”Rumble Fish”には、若者たちの心の影を捉えた青春群像劇と云っても、ジム・ジャームッシュ監督の”Down By Low“や、デニス・ホッパー監督の”イージー・ライダー“、エドワード・ヤン監督の”恐怖分子“、石井聰亙監督の”狂い咲きサンダーロード“や、ジャン=リュック・ゴダール監督の”はなればなれに“のような、監督自身が最強のトリックスターとして奔放に振る舞い、若者たちと共に傷つき、共に斃れ、魂の彼岸への長い旅路を、永遠の端緒への絶え間ない希求を、共に煩い、共に慈しみ、共に還ってゆく凄まじい作品とは、違った趣があります。
これは、どちらが良い、悪いと云う話ではなくて、若者たちと共に負け、共に苦しみ、共に斃れると云う姿勢と、若者たちの負け方を愛し、理解し、考え、自らの文体で誰かに伝えようとする姿勢は、全く違ったアプローチであると云うことです。
小生は本作”Rumble Fish”や、若い頃に観た”La Fin Du Jour”を、あくまでも境界の向こうへ突き抜けて行く、表裏一体の翼を持った墜落天使としての若者たちへの憧憬の視線、そうした自由な精神への、頑迷な後悔のような、甘い憧れの視線の、表出であるように感じました。1983年という、原色のフィルムばかりが世界中を飛び回っている時代にも関わらず、モノクロームの映像に固執し、水槽の中の”Rumble Fish”にだけ、紅の、青の、目の醒めるような色をつけた監督の心は、モノクロームに見えてしまう手に入らない憧れの世界への、幻想の顕れをその魚の色味に託したのではないかと思います。
空瓶と、煙草の吸殻と、吐き捨てられた唾と、泥水と、落書きだらけの朽ちたコンクリートがくすぶる裏路地を、1983年の空気の中では、ずいぶん季節外れなモノクロームの色彩で、叙情的に捉えたカメラは、Stephen H.Burumの手によるもので、偶然ですが少し前に再見した小生が大好きなブライアン・デ・パルマ監督の”Sneak Eyes”と同じ撮影監督でした。デ・パルマ中期の名作”The Untachable“の撮影も、Stephen H.Burumが手掛けられています。
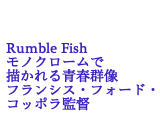
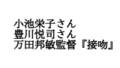

コメント